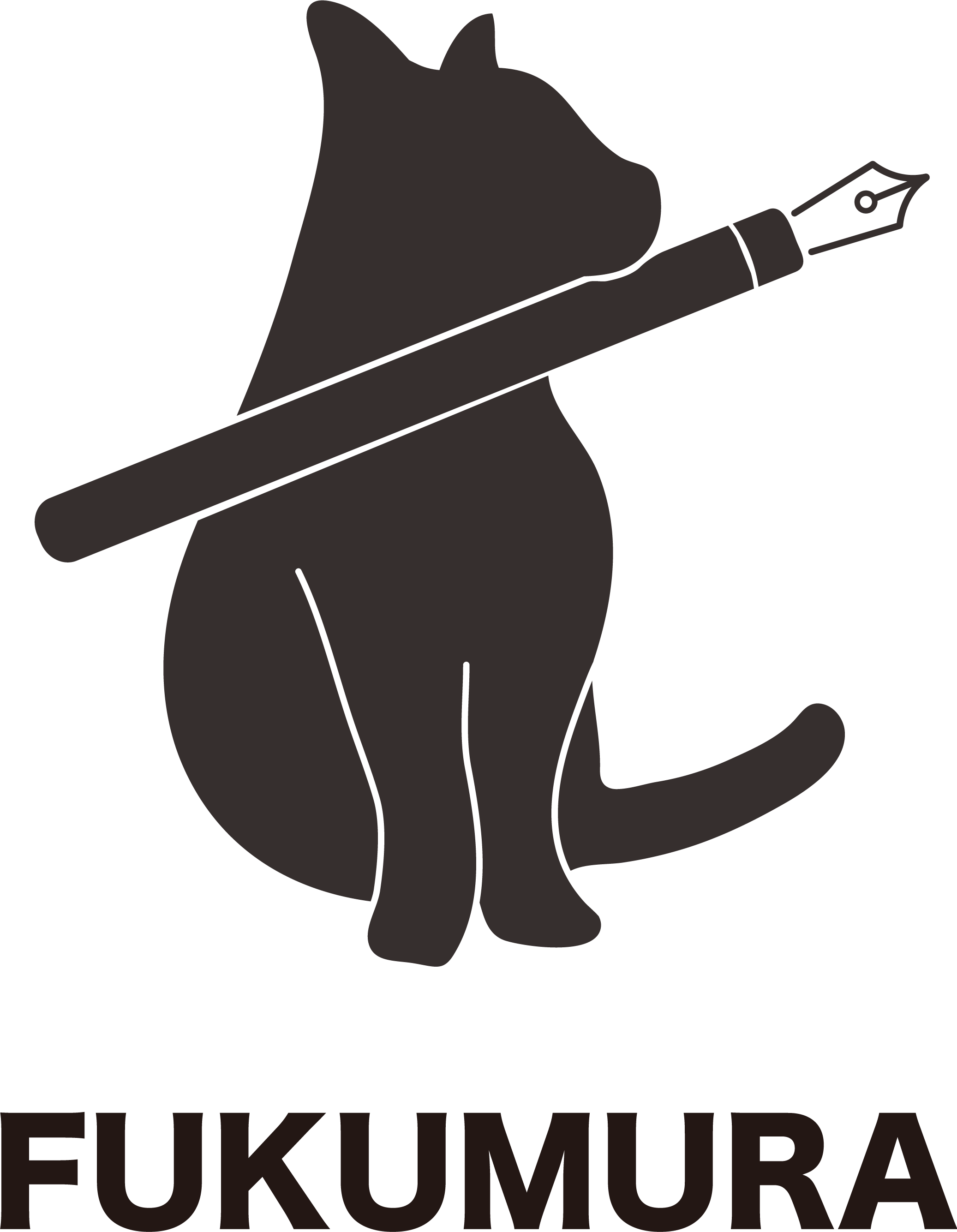講座概要|まさか!に親子で備える終活講座
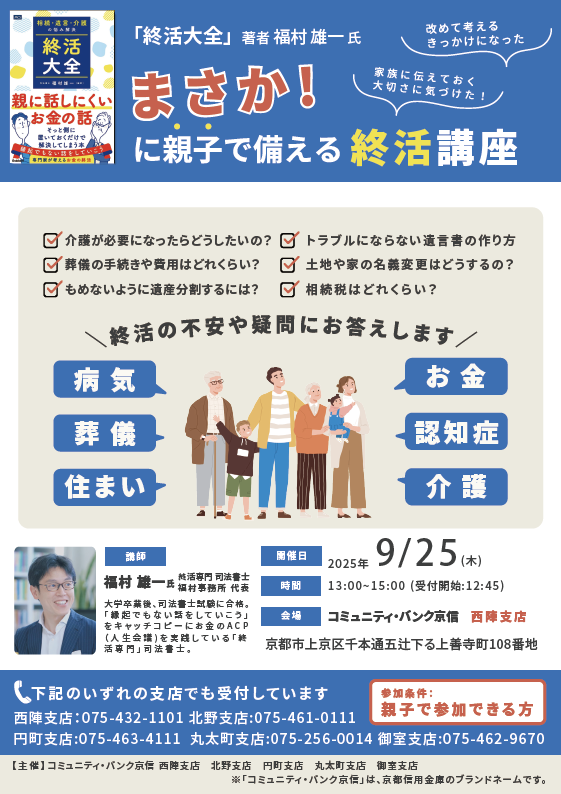
まさか!に親子で備える終活講座(初級編)
― 西陣・北野・丸太町・円町・御室の5支店合同/会場:京都信用金庫 西陣支店 ―
これまで各支店ごとに開催してきた終活講座。
今回はじめて、5支店が連携し、エリア合同開催として実施しました。
会場の京都信用金庫西陣支店には多くの方が集まり、世代を超えて「終活」について語り合う貴重な時間となりました。
第一部:【学ぶ・知る】終活と切っても切れないお金の話|司法書士 福村雄一
“ちゃんと備える”って、どういうこと?
前半は、司法書士 福村雄一による講演「終活と切っても切れないお金の話」。
「まだ元気だから大丈夫」と準備を後回しにしてしまうことのリスクや、遺言書を残すことで家族の負担を減らせることなど、具体的な事例を交えて解説しました。

- 終活を考える上で大切な4つのテーマ
- 「まだ元気だから大丈夫」と準備を先送りにするリスク
- 家族構成によって変わる「法定相続人」の話
(例:子どものいない夫婦は、義両親や兄弟姉妹が相続人になることも) - 生前贈与や生命保険の非課税枠など、知っておくと安心なお金の知識
第二部:【話す・深める】テーマ別サロン対話
第二部は、参加者が気になるテーマを選んで相談できる時間。
参加者が関心のあるテーマごとに分かれ、専門家と少人数で話せる「テーマ別相談会」を実施しました。
たとえば、
「相続や遺言書について、具体的にどう備えたらいいか知りたかった」
「終活の周りのことを漠然としかわかっていなかったので、しっかり理解したい」
といった参加者の声に、各分野のアドバイザー(税理士・ソーシャルワーカー・葬祭ディレクター・福祉宅建士・司法書士)が丁寧に耳を傾け、アドバイスを行いました。同じテーマに関心をもつ人同士で話すことができたことで、「うちだけじゃなかったんだ」「家族とも話してみようと思えた」など、安心と気づきのある時間となりました。

テーマ:【終】お葬式、どうしたい?
葬祭ディレクター |株式会社 まるいち 福岡 圭吾
‐ 葬儀費用や最近増えている直葬式の事例
‐ 墓じまい・仏壇じまいの進め方
‐ 葬儀会社の仕組みについて など
テーマ:【病】もしもの時に必要なこと
ソーシャルワーカー|社会福祉法人 京都社会事業財団 西陣病院 相談員
‐ 認知症や介護に関する相談
‐ 介護保険制度や要介護認定の流れ
‐ 施設の種類や費用感、地域の支援サービス など


テーマ:【住】安心して暮らし続けるために必要なこと
福祉宅建士 |久保 有美
‐ 空き家や自宅の名義・境界の確認
‐ 高齢期の住み替えや住まいの選択肢
‐ 火災保険証書など重要書類の整理・保管方法
テーマ:【税】知らないと損する相続税の話
税理士|税理士法人 京都財務サポート 代表・税理士 三木 康弘
税理士|税理士法人 京都財務サポート 代表・税理士 小林 秀樹
‐ 相続税の基礎控除と申告の要否
‐ 生前贈与の基礎控除や法改正の注意点
‐ 生命保険の非課税枠(500万円)の活用法など


テーマ:知らないと損する相続税の話
税理士|あおぞら税理士法人 税理士・CFP 新見 明子
‐ 相続税の基礎控除と申告の要否
‐ 生前贈与の基礎控除や法改正の注意点
‐ 生命保険の非課税枠の活用法など
テーマ:【財】遺言書で遺す想いと資産
司法書士 |福村雄一
‐ 遺言書の役割と作成時の注意点
‐ 直筆遺言と公正証書遺言の違いとメリット
‐ 遺言執行者を指定する重要性 など

第三部:【行動・動き出す】次の行動ワーク
チェックリストを用いて「自分に足りない準備」「今日からできる一歩」を明確化。
「遺言書の下書きをしてみる」「書類の所在を家族と共有する」など、
元気なうちから少しずつ、大切な人と自分が安心できることを行動に移すきっかけとなりました。

- 相続について
- 老後の資金や保険について
- 病気や認知症について
- 葬儀やお墓について など
終活講座で寄せられた「これはうちも他人ごとじゃないかも…」と思わずハッとする質問と事例
- Q遺言書は必要ですか?
- A
アドバイス:遺言書があった方が効果的です。特にお子さんがいらっしゃらないご夫婦の場合、義理の家族が相続人になることがあり、遺言書があるとお金の問題が解決しやすくなったり、話しやすくなったり、多くの場面で役立ちます。
- Q遺言書を作成する際のポイントは?
- A
アドバイス:財産を特定できるようにすることが大切です。全財産を相続させる場合は具体的な財産の特定は不要ですが、個別の財産を指定する場合は財産の種類に応じて特定することが大切です。また、遺言執行者を指定することも重要です。
- Q公正証書の遺言と自筆の遺言の違いは?
- A
アドバイス:公正証書遺言は公証役場で作成し、証明力が高いですが費用がかかります。自筆証書遺言は手軽に作成できますし、書き直すのも簡単です。法務局に届け出ることで死後の裁判所のチェック(検認)も不要になるので、まず最初の遺言は自筆で作成してみるのもよいです。
- Q生前贈与の非課税枠は?
- A
アドバイス:生前贈与の非課税枠は年間110万円です。贈与税がかからない範囲で贈与できます。今日は(税)のブースで税理士の先生に相談できるので、ぜひ相談してみてください。
- QQ:遺言書がない場合、相続はどうなる?
- A
アドバイス:遺言書がない場合、法定相続人が相続することになります。個別に財産を分けるには、相続人全員の合意が必要で、手続きが複雑になることがあります。
- QQ:自筆の遺言書の保管方法は?
- A
アドバイス:自筆の遺言は手数料3900円で法務局に保管してもらうことができます。あらかじめ指定した人に遺言書が保管されていることの通知が行くようにすることができ、裁判所の検認も不要になります。
自宅で保管しておく場合は、原本がなくならないように注意することが大事です。相続の後に裁判所での検認が必要です。。
参加者のお声を一部ご紹介
- 「普段なかなか話せないことを相談できた」
- 「チェックシートで“やること”が整理できたので、家族と話してみようと思った」
- 「支店から案内が届き、参加のきっかけになった」
講座を終えて
終活は「暗い準備」ではなく、家族と前向きに将来を共有する大切な時間です。
今回の合同開催は、支店を越えて学びとつながりを広げる新しい試みとなりました。
今後も地域の皆さまとともに、“話しにくいことを話しやすく”する場を育んでいきます。